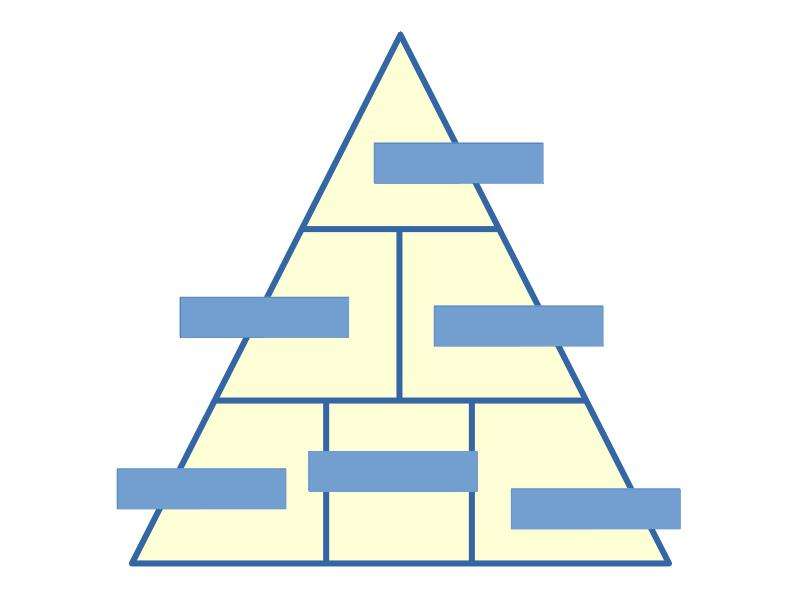篠田統著「すしの本」を読みました。
本書は、すし(お寿司)について、その歴史や地域の広がり(日本国内だけでなく一部は海外も)をまとめた本です。
1940年代に出版された、いわゆる名著です。
本書は一般向けに書かれています。
著者の篠田さんも、家族に読んでもらいながら推敲したそうですから、かなり読みやすいと思います。
本書の特徴は、とにかく現場主義ということです。
日本全国のお寿司について、地元の学校でアンケートを取ったり、老舗のお寿司屋さんからインタビューを取ったりしています。
また、歴史については中国の歴史書から読み始め、日本の古典に至るまで調べています。
本書の構成は、以下の通りです。(表記は原文のママ)
第1編 すしの調理学
- すしの種類と分布
- 馴れずし
- 生成(なまなれ)
- いずし
- 姿ずしと棒ずし
- 飯ずし
- 握りずし
- 散らしずし
- 巻きずし
- 卯の花ずし
- そのほかのすし
- すしの材料
第2編 すしの生化学
- 馴れずし
- 生成
第3編 すしの食物史
- 古代シナのすし
- 漢・魏・六朝
- 隋・唐
- 北宋・南宋
- 元・明・清
- 古代日本のすし
- 室町から安土へ
- 元禄のころ
- 田沼時代前後
- 近世のすし
補編 大阪ずし
- 阿部直吉老人聞き書き(抄)
目次の構成から、3編に分かれていますが、第2編は、さらっと飛ばされる感じなので、実質的には、以下の2つがメインコンテンツです。
- 第1編の、日本の地域ごとのお寿司の種類
- 第3編の、中国と日本のお寿司の歴史
お寿司といえば、江戸前の握りずし(酢飯の上に生魚が載ったすし)がまずは思い浮かびます。
が、実際にはもっと種類があります。
わたしの読んだ本は、柴田書店の版ですが、そのp26に系譜図があります。
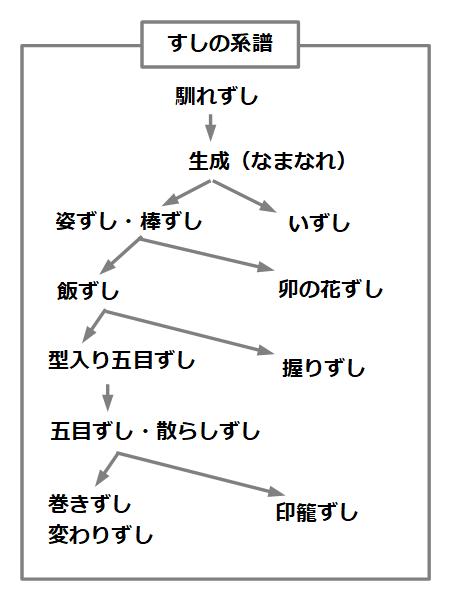
ちなみに、具体的には以下のようなお寿司がある(あった?)ようです。
- 馴れずし:滋賀県フナずし
- 生成:和歌山県馴れずし、兵庫県ツナシずし
- いずし:石川県・加賀蕪ずし、秋田県ハタハタずし
- 姿ずし・棒ずし:京都サバずし、大阪スズメずし、奈良県・吉野アユずし
- 卯の花ずし:山口県とうずし、島根県・石見おまんずし
- 飯ずし:コケラずし、箱ずし
- 握りずし:江戸前ずし
- 型入り五目ずし:長崎県大村ずし
- 五目ずし・散らしずし:岡山県備前ずし
- 巻きずし:ノリ巻き、コンブ巻き
- 印籠ずし:稲荷ずし、三重県和歌山県・熊野めばりずし
- 変わりずし:ソバずし、竹ずし、洋食ずし、などなど
上記は、具体例の一部であり、本書にはもっと多くの事例が紹介されています。
ただし、本書執筆時点(昭和40年代)でさえ、途絶えてしまったお寿司があるようですから、いまもこれらのお寿司が食べられるかは、分かりません。
馴れずしなんて聞いたことありませんでしたが、フナずしのことだったんですね。
生化学的には、魚とお米を嫌気発酵させて乳酸を生み出し、それを食べるのが馴れずしらしいです。
つまり、発酵食品なので、食べごろがあるのですね。
買ってすぐ食べるのと、何時間か置いてから食べるのとでは、おいしさに違いがあるようです。
乳酸だから、もちろん酸っぱいわけですが、酢酸とは、もちろん味が違うんでしょう。
わたしはフナずし食べたことないので、今度食べてみたいです。
江戸前の握りずしについては、しょうゆのつけ方だの、注文の仕方だの、うんちくをたれたがる方々がいます。
本書は、そういう「うんちく」的な本ではありません。
お寿司について、見通しよく全体が見渡せるようになります。
そしておそらく、お寿司に対する見方が大きく変わることでしょう。
ぜひ読んでみてください。